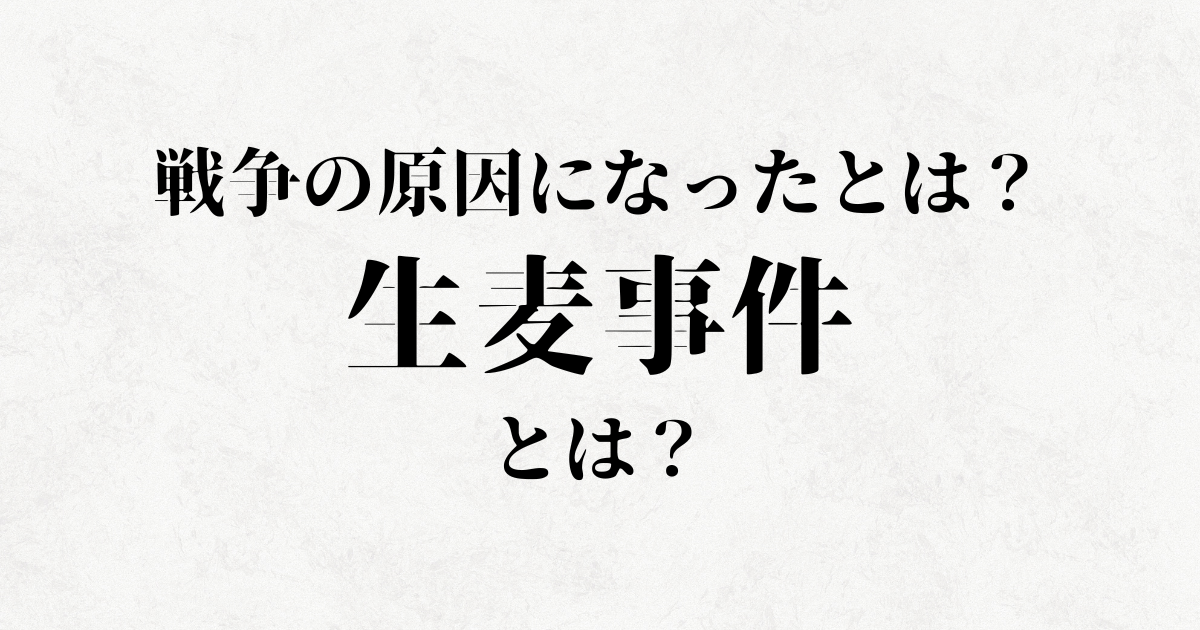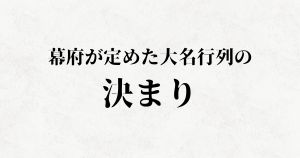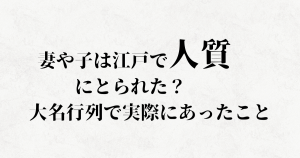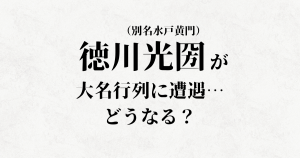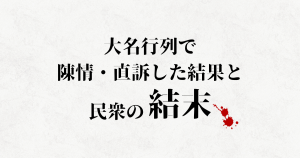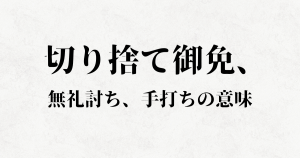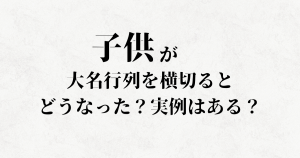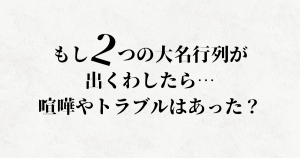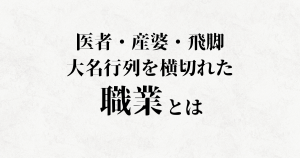歴史の授業で学んだ「生麦事件」を憶えていますか?
その後に起きた薩英戦争の方が有名なため、なんとなく字面の記憶はあっても詳細については不明です。
幕末に藩の隊列を横切った外国人を、無礼と怒った藩士が切り捨て御免した事件と憶えている人が多いです。
世界史も同時に学ぶため、やはり少し文明的に遅れていた日本の分が悪かったのではというとらえ方でした。
江戸時代は刀を携えた武士による“無礼打ち”があったことは有名で、当時の話としてさほど驚きは感じません。
実際、尊王攘夷の思想で荒ぶる京では、政治的な殺傷事件や無差別テロのような殺人事件が頻発している不穏な時代でした。
しかしその一方で、町人文化は江戸を中心に爛熟し、訪れた外国人がその様子を整然として活気に満ち、絵のように美しかったと伝えています。
支配階級である武士の振る舞いも物静かで礼儀正しく勤勉、統制がとれており生活は意外にも質素で慎ましかったとも。
そのような折、起こるべくして起きてしまった「生麦事件」は、図らずも一気に薩英戦争の原因となり、開国へ向け大きく動いて行くことになりました。
生麦事件は、誰がどう悪かったのかが取りざたされることが多いのですが、本当のところどうなんでしょうか。

生麦事件の概要・その理由
黒船到来から数年後となる1862年(文久2年)8月、朝廷勅使の護衛役として江戸に下向しその帰途にあった薩摩藩主の父島津久光率いる約400人の行列が、武蔵野国生麦村(現在の横浜市鶴見区)付近で異人切り事件を起こしました。
事件の被害者は、香港在住の婦人1人、上海の商人1人、横浜居留地の商人2人、計4人のイギリス人達でした。
横浜居留地から騎馬で出かけた彼らはの目的は、川崎大師への観光です。
その日は大名行列が通行する予定があり、遭遇すると面倒だと友人から中止を忠告されましたが、アジア人の扱いは慣れていると言い出発しました。
薩摩藩の一行は、道中進行方向にこの4人と遭遇すると手招きして引き返す様合図しましたが、彼らは脇によけただけで直前まで引き返さず、やがて先頭に居たリチャードソンの馬の首が行列に触れてしまいます。
そこで薩摩藩士奈良原喜左衛門に無礼打ちされたチャードソンがその後に死亡、クラークとマーシャルは重傷を負いながらアメリカ領事館に逃げ込み、難を逃れたボローデル婦人は居留地に戻りました。
無礼な異人を切ったというこの事件の知らせは、皮肉にも公武合体を推進するため江戸に訪れていた島津久光の思惑に反し、これまで弾圧していた尊王攘夷派に刺激を与えると同時に勢いを増すきっかけとなりました。
なぜイギリス人達は無礼打ちされたのか
以下の事件に関する証言と記録の詳細は、幕府と薩摩藩側のみばかりとなるため正確さに欠けるとされていますが、当日のリチャードソンが死亡に至るまでの様子を街道沿いの茶屋の女性が目撃しているようです。
街道において進行方向から外国人4人の騎馬がやってきたため、直ぐに下馬して脇に退くよう、何度も身振り手振りも交えて伝えたがいっこうに彼らは言う事を聞かず、しまいには行列の間に入り逆走する形となりました。
さらには駕籠近くまで近づいたため、側近くの藩士らが堪えきれず無礼打ちをし、瀕死の重傷を負って下馬した外国人に対し介錯したとあります。
単に行列を横切ったのではなく、静止を受けても無視しそのまま進行、間近に近づき駕籠近くまで進んでしまったようです。
この時先頭を行くリチャードソンは、流石に殺気立つ周囲の様子に慌てて引き返そうとするも、騎馬のため思うような行動がとれずかえって列を大きく乱し混乱を招くことになった様子です。
薄かった日本の文化への知識と観光目的での滞在
被害に遭ったイギリス人は、アヘン戦争に敗北後の中国(清)から英国領となる香港在住者や上海の商人2人を含む観光目的訪れた一般人であり、アジア人に慣れていたつもりでも日本の慣習に疎かった様子です。
通訳もついていないため言葉も通じず、条約の治外法権で騎馬も許されていたことから馬から降りる必要はないと思っていたようです。
特にリチャードソンの素行はあまり良くなく母国や上海でも粗暴だったという証言もあるため、植民地独特の優越感のままの気分でいたのかも知れません。
よりによって当時最強の武力を誇る薩摩藩の行列に遭遇
この日イギリス人が遭遇したのは、関東近辺のコンパクトで省エネを図っている小藩の行列ではなく、よりによって当時最強の武力を持つ薩摩藩島津久光の行列でした。
薩摩藩は、江戸幕府から遠く離れる外様でありながら地の利を生かし交易により最強の武装、沖縄諸島を支配下に置き黒砂糖の専売で財力を持っていました。
久光は藩主である自分の息子の後ろ盾となり、自ら国父を称し周囲にも呼ばせた豪胆な人物でした。
しかしその野心と強引な行動力は、かえって江戸幕府から将軍の座を狙う人物として警戒されます。
島津久光は勅使という天皇の使いと共に、公武合体を推進するべく江戸に来ていました。
公武合体とは、朝廷と幕府が一緒になって政治を行うことで、将軍の跡継ぎとして徳川慶喜を推す一橋派による幕府の人事改革を行った後の帰路でもありました。
幕政にも関与を望んだ久光は拒まれ、苦渋の面持ちでした。
国元やこれから向かう京は尊王攘夷運動(天皇を尊敬し外国勢力を日本から追い出そうとする思想や主張)の真っただ中にあり、ピリピリした緊張感のある武装集団でもあったのです。
無礼打ちをした藩士はノイローゼ状態だった!?
他に考えられる理由に、無礼打ちをした藩士が今でいうノイローゼ状態であったとの記録も見受けられます。
直接事件を起こした藩士は、精神的そう弱な状態であったとされ、どうも事件の沙汰を受けていないようです。
黒船到来後の不穏な社会情勢と、武家社会が根本から揺らぎ覆されるような不安感やストレスにより心神過敏の状態、ノイローゼであった、もしくは元来そのような病因を持つ人物であったと幕府に報告がなされたようです。
幕府はこの件に関し、気が変な者を取り締まることはできないと、それ以上の追及をしなかったようです。
海外の反応と当時の証言
この時期の日本を取りまく世界情勢として、日本に開国を迫る諸外国には交易とは別に植民地化のもくろみもありました。
イギリスは中国(清)とのアヘン戦争・アロー戦争に勝利し北京が陥落、香港を植民地にし勢いのある状態です。
アメリカでは、南北戦争、初代大統領リンカーンが奴隷解放宣言を行う直前の激動の時期です。
フランスは、ベトナムの植民地化に成功しつつあり、虎視眈々と日本国内の情勢を見極めている様子でした。
日本は国土が乏しく、かつては産出した貴金属類の鉱物資源は既に長年にわたる不平等な取引により放出し枯渇し始めており、インドやアフリカのスパイスや茶葉、カカオのような魅力的な植物の発見はありませんでした。
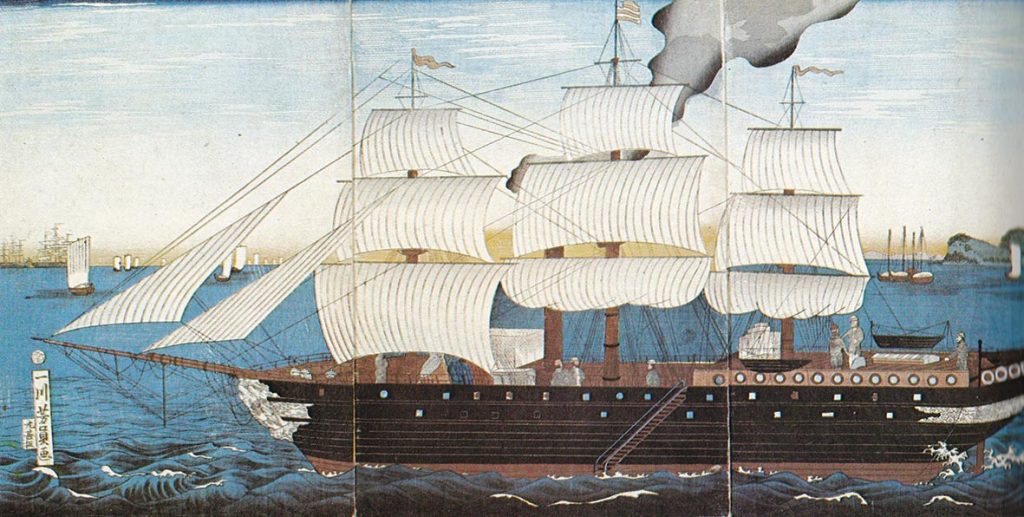
イギリスの反応
条約に規定されていた遊歩地城内で、白昼イギリス人が殺されたことにイギリスは激怒しました。
横浜の外国人居住地では、薩摩藩との戦争をも辞さない雰囲気が募ったものの、その時点でイギリス海軍の戦力に不足があることを懸念し交渉に持ち込みました。
幕府の責任を追及し10万ポンド(約20億円位)の賠償を要求、複数の軍艦を横浜港に入港して威圧、幕府の老中による独断専行支払い(後に引責辞職)をさせます。
これでも治まらず、地方藩の勢力を抑えられない江戸幕府の統率力を疑い始め、幕府の要望を拒否して薩摩藩と直接交渉を始めます。
艦隊を鹿児島湾につけると、生麦事件の犯人逮捕と処刑、償金2万5千ポンド(約5億円)の支払いを要求するも薩摩藩が拒否すると、交渉を断念し薩英戦争が勃発しました。
イギリス祖国のリチャードソンの叔父は事件の知らせを聞くと、頑固であった甥はいつかそのような死に方をすると思っていたと述べ、島津は間違っていないと思うと語りました。
イギリス代理公使は、リチャードソンは、騎士道的な本能のある蛮勇な人物であったことを述べています。
アメリカの反応
ニューヨークタイムズ紙では、日本の主要な道路で主要な大名に無礼な行いをしたリチャードソン達の方に非があると報道しています。
日本人ですらこのような振る舞いは許されないとしています。
また、同日に薩摩藩の行列と遭遇したアメリカ人商人ヴァン・リードは、脇道によけて下馬し帽子を取って敬意を表す所作をしており難なくやり過ごしています。
ヴァン・リードの見解は、傲慢な振る舞いで自らが招いた災難であると述べています。
日本を訪れていた外国人宣教師や商人達にとって、街道で出くわす大名行列は面倒なパレードでしたが、一定のルールと礼節を守っていれば問題はない周知のことだったようです。
理由なき無礼打ちはなかった!?海外より驚いた江戸幕府の反応
生麦事件に一番驚いたのは、当時日本に渡航していた海外の国々ではなく、当の江戸幕府と武家社会でした。
江戸時代はご存知士農工商の階級社会ですが、その頂点に立つ武士の人数はそれほど多くはありません。
そのため、実際の現場を取り締まる役目は、町人による組織にゆだねられていました。
江戸で横行し恐れられていた“辻斬り”は、武士の違法な殺人行為とみなされ厳しく取り締まられていました。
このような武士道に堂々反する行為は、現代のサイコパスのような精神的・性格異常者のような捉え方でした。
そのため、これまで政治がらみによる外国人の殺傷事件はあったものの、所業の良くない浪士ならともかく、大名行列に加わるような藩士が無礼打ちしたケースは初めての事でした。
関東や江戸ではない、同じ武士なのに著しく待遇が違う上下関係は、西南の四国九州ではよく見られる光景でした。
事なかれ主義で役人的、どこか現代にも通じる部分がある江戸の武士に比べ、西南の下級武士や次男三男の行き場のない武士の不満や尊王攘夷思想は生麦事件によっても盛り返しました。
公武合体を推進していた薩摩藩は、寺田屋事件などで攘夷派弾圧をしていたにもかかわらず、その機運がまたも高まってしまったのです。
心中の思惑とは別に京に到着すると朝廷では褒め称えられ、街道の沿道でも「流石、薩摩様」と声援をおくられたのでした。

約160年前、閉ざされた最果ての地日本で起きた生麦事件。
昔であろうが今であろうが、大統領のパレードの最中に制止をきかず(言葉や習慣が理解できず)、警備の隊列の中を逆走してスピンしたら射殺を余儀なくされます。
薩摩藩や幕府は、最後まで犯人である誰かが悪いとつきだして処刑をすることなくしらを切り続けました。
理由は、文書の翻訳や薩摩弁の通訳が難解で、藩主に責任を問うと誤解したためとも言われています。
刀や銃等を常に携える人は、一時の感情の高まりで武力を行使しないよう、心と体を鍛える鍛錬が必要と言われますが、国や慣習、言葉、価値観が違うとどうにもならない時があります。
生麦事件が起きたのは、当時でもありがちなことやそれが当たり前の世の中でなかったからこそ、今でも事件の現場に石碑が置かれ大切にされ、後世に長く伝えられているのに違いありません。
江戸時代末期ならではの事件だと思ってたら、そうじゃなかった感でズッシリ来ました…。